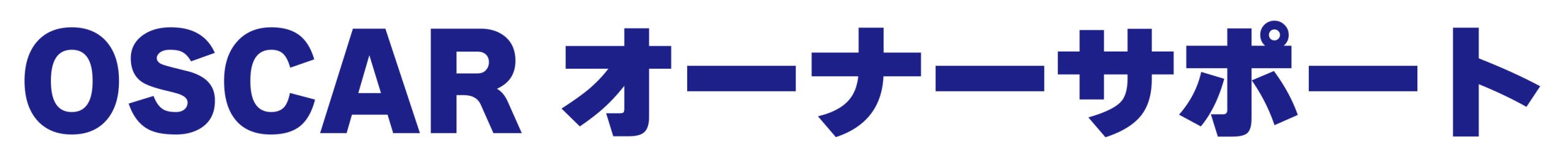防災対策について再確認【前編】

今回はあらためて防災対策について再確認してみましょう。少し長くなりますので、前後編で分けてお話ししたいと思います。まずは【前編】として「防災の準備」についてお話いたします。
目次
【前編】
-防災グッズの準備
- 非常持ち出し品
- 非常用備蓄品
-ハザードマップの事前確認
- ハザードマップとは
- 避難所と避難場所の違い
- 事前確認と注意点
【後編】
-避難について
-避難情報の伝えられ方
-警戒レベルごとの避難行動
-避難をすると
防災グッズの準備
非常持ち出し品
避難所や避難場所に避難するときに持ち出すものです。速やかに移動できるように、必要なものや貴重品に限りましょう。
また、すぐに持ち出せるようにリュックなどに入れておき、逃げ出す時の通り道や、寝室の枕元などに置いておきましょう。


非常用備蓄品
在宅避難をするときに必要な備蓄品です。最低でも3日分、可能であれば1週間分の備蓄をしておくとよいでしょう。
消費期限のあるものはローリングストック(消費期限が近付いたものを使い、その分を買い足す方法)で無理・無駄のない備蓄をしましょう。


食料や飲料水などの消費期限があるものは期限切れにならないように、消費期限管理用のアプリを利用すれば管理しやすいでしょう。
ハザードマップの事前確認
ハザードマップとは
自然災害での被害のおよぶ範囲や程度を色分けして示してあり、さらに避難所や避難の道筋などが表されている地図です。自治体で作成していますので、インターネットで「(自治体名を入力) ハザードマップ」で検索すれば探すことができます。

災害時に慌てないためにも、日ごろからハザードマップや避難所・避難場所の位置を確認しておきましょう。
避難所と避難場所の違い
避難所
災害時に自宅で生活できなくなった場合に、一時的に避難生活する場所です。学校や公民館などが指定されています。災害の種類(地震、洪水、土砂災害など)によって指定場所が対応していない場合もありますので注意が必要です。
避難場所
火災や津波などから、急いで身を守るために避難する場所です。大きな公園や高台などが指定されています。
事前確認と注意点
自宅や勤務先周辺のハザードマップで被災想定区域を確認しておきましょう。ただしマップで色が塗られていない箇所でも、必ず安全とは言えません。中にはハザードマップの整備が間に合っていない場合もあります。
また、いざという時に速やかな行動ができるように、避難所や避難場所を確認しておきましょう。
地図は印刷して携帯しておくか、防災リュックに入れておきましょう。地図データをスマートフォンなどに保存しておくのも良いでしょう。ただし被災時にはネットワーク障害などで検索できない可能性がありますので、必ず事前に確認しておきましょう。
さて、今回の「防災の準備」については、ここまでとなります。次回は【後編】として「避難」についてお話ししたいと思います。